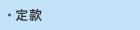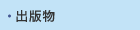25年8月26日更新
 2025年「すべての人の社会」8月号
2025年「すべての人の社会」8月号
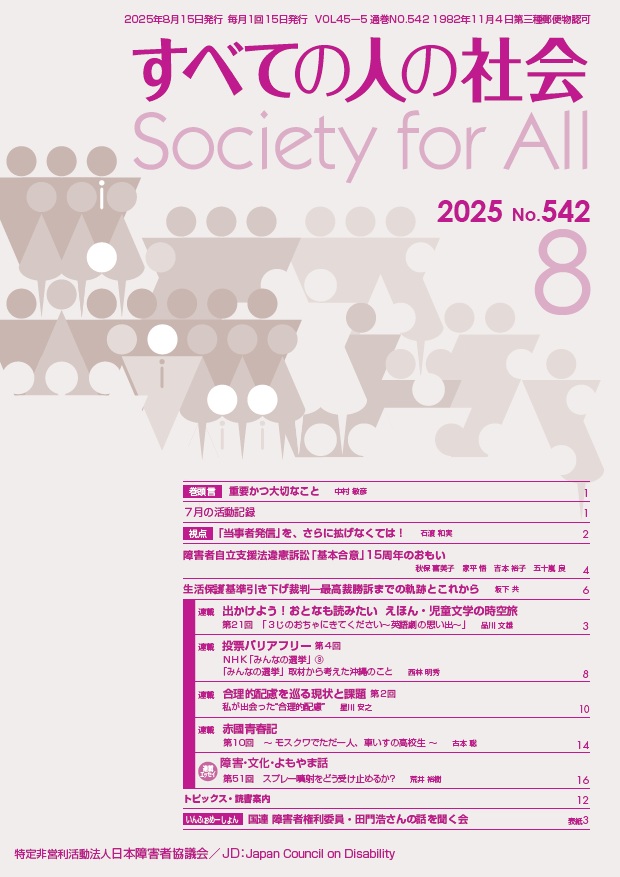
VOL.45-5 通巻NO.542
■巻頭言 重要かつ大切なこと
JD理事 中村 敏彦
障害者総合支援法は、障害者が自立した生活を送れるように支援することを目的としており、「誰もが平等に基本的人権を持ち、個人として尊重されること」、「分け隔てられず、人格と個性が尊重される共生社会を実現すること」、「身近な場所で必要な日常生活や社会生活を営むための支援が受けられること」、「社会参加の機会が確保されること」、「どこで誰と生活するかを選択でき、地域社会で他の人々との共生が妨げられないこと」、「日常生活や社会生活を営む上の障壁の除去に資すること」。
まさに、障害者権利条約を実現するための理念でありますが、社会には根本的な課題が多く残っています。
①差別・偏見
国は、障害者に対する差別や偏見について、障害者差別解消法などを制定して取り組んでいますが、国民の理解や配慮は十分とは思えません。最高裁で全面勝訴した(旧)優生保護法は、被害者への謝罪・救済では解決しません。国を挙げて障害者の存在を否定し、差別や偏見を国民に教育し、今日の差別や偏見の基礎を作りました。その責任は重大であります。改めて、障害者への偏見と差別について、人権倫理に基づいた国民への再教育が必要です。
②経済的自立
障害者の経済的自立が厳しい状況であることも大きな問題です。一般就労も増えていますが、福祉サービスで働く人の多くは、低水準の工賃しか受け取れていません。年金改革法は、障害年金の大切な点が放置されたまま成立しました。判定の仕組みに疑念の声が挙がる中、衆・参両院の付帯決議は、その透明性の確保が強く求められました。
③支援体制不足と地域格差
障害者のニーズに合わせて、国はさまざまに支援体制を整えています。しかし、十分に機能しているとは思えません。特に、障害者の地域移行・地域生活を支える地域生活支援拠点においては、必要量が圧倒的に不足しているのが実態です。事業の実施主体を市区町村任せにしていることを背景に、財政状況などの影響で格差も生まれています。当事者や地域の声に耳を傾けた対策が必要だと思います。
④大切なこと
去る6月2日に障害者自立支援法違憲訴訟「基本合意」15周年記念フォーラムが開催され、当時を振り返る良い機会となりました。改めて、「基本合意文書」や障がい者制度改革推進会議総合福祉部会による「骨格提言」には、重要で大切なことがたくさん詰まっていることを強調しておきます。
■視点 「当事者発信」を、さらに拡げなくては!
JD副代表 石渡 和実
3月26日、東京・八王子のヒューマンケア協会の中西正司さんが逝ってしまわれた。享年80歳。日本のみならず、世界の自立生活運動のリーダーであった。同協会の機関誌6月号にお別れ会の様子とともに、スタッフによる追悼の言葉が紹介されている。どなたも中西さんの言葉に、行動に、突き動かされ、走り続けてきた想いを綴っている。
筆者にとっても大きな存在であった。2003年発刊の上野千鶴子さんとの共著『当事者主権』(岩波新書)の文章は、しばしば引用させていただいた。「当事者とは『問題を抱えた人』と同義ではない。問題を生み出す社会に適応してしまっては、ニーズは発生しない。…こうあってほしい状態に対する不足ととらえて、そうではない新しい現実をつくりだそうとする構想力を持ったときに、はじめて自分のニーズとは何かがわかり、人は当事者になる。…当事者主権は、何よりも人格の尊厳に基づいている。」障害者権利条約が採択される3年前であるが、まさに社会モデル・人権モデルに立脚した人間観である。
筆者は今年度から、東京都自立支援協議会の活動に関わっている。都内区市町村の協議会をつなぎ、牽引する立場とも言えよう。この協議会では合理的配慮に基づく「当事者参画」を柱に、地域生活支援や相談体制について検討を続けている。当事者の視点からの発信が、地域課題を浮き彫りにし、その解決に向けた流れを創り出していることを実感する。
先日の会議では、車椅子利用の委員が小学生の頃の体験を語った。介護員の支援を受けながら通常学級で学び続けたという。介護員の行き届いた支援に感謝しつつも、「今はこの場を離れてほしい」と感じたことがしばしばあったという。大人のいない場で、子ども同士の会話や行動が大きな意味をもち、子どもの成長につながることは多い。しかし、介護員の熱心さゆえに離れることなどなかったし、「いないで!」と言い出すこともできなかった。
今、大人の意思決定支援と同様、子どもの意見表明等支援が注目されているが、改めて子どもの秘める力、人格の尊重などについて考えさせられる機会となった。こうした気づきや発見は、「障害のある子ども」としての実体験を伝えてもらえたからこそ見出せるものである。人間関係や社会システムに関する重要な指摘であり、変革へとつなげたい。
7月6日、鉄道弘済会の第61回社会福祉セミナー講座②は、「当事者発の支援論」がテーマであった。「全盲弁護士の視点」というタイトルで、大胡田(おおごだ)誠弁護士が登壇した。司法試験をめざして大学で勉強していた時、「点字を打つ音がうるさい」という訴えがあったので教室の隅に行くように、と教授が指示したという。すると、「そんなのおかしい、うるさいと思った人が動けばいい」という声があちこちからあがった。こうした体験を重ねたことが、弁護士として人権を守る大きな力にもなっている。障害があることを「弱み」ではなくポジティブに捉える、そんな関係性や支援のあり方を気負うことなく語ってくださった。
こうした発信は、障害のある人が障害のない人と場を共にしているからこそ可能となる。それが地域を、社会を変えていく大きな力となる。今回は身体障害がある方ばかりの紹介となったが、知的障害の方も精神障害の方も自信をもって声を挙げている。「当事者発信」の意義を地域全体で認識し、拡げていくことが、「誰一人取り残さない」社会を実現することにつながる。障害のある人も、認知症のお年寄りも、小さな子どもも、外国にルーツがある人も…、みんながどんどん声を挙げよう! それを受け止められる地域を築こう!
■2025年7月の活動記録
■障害者自立支援法違憲訴訟「基本合意」15周年のおもい
秋保 喜美子 家平 悟 吉本 裕子 五十嵐 良
■生活保護基準引き下げ裁判―最高裁勝訴までの軌跡とこれから
坂下 共(きょうされん事務局次長 / いのちのとりで裁判全国アクション事務局)
■連載 出かけよう!おとなも読みたい えほん・児童文学の時空旅
第21回 「3じのおちゃにきてください~英語劇の思い出~」
品川 文雄(発達保障研究センター前理事長 / 元小学校障害児学級教諭)
■連載 投票バリアフリー 第4回
NHK「みんなの選挙」③
「みんなの選挙」 取材から考えた沖縄のこと
西林 明秀(NHK報道局選挙プロジェクト記者)
■連載 合理的配慮を巡る現状と課題 第2回
私が出会った“合理的配慮”
星川 安之(共用品推進機構専務理事・事務局長)
■連載 赤國青春記
第10回 ~ モスクワでただ一人、車いすの高校生 ~
古本 聡(翻訳業)
■障害・文化・よもやま話 第51回
スプレー噴射をどう受け止めるか?
荒井 裕樹(二松学舎大学教授 / 障害者文化論研究者)
■トピックス・読書案内
■いんふぉめーしょん
賛助会員大募集中!
毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。
■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)
■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)
★1部300円(送料別)からお求めいただけます。
▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347
○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp
○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】
※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。
※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。
フッターメニュー