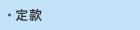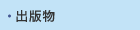25年2月20日更新
 2025年「すべての人の社会」2月号
2025年「すべての人の社会」2月号

VOL.44-11 通巻NO.536
■巻頭言 能登半島地震災害から1年
避難所におけるバリアフリー化と重度障害者の課題
JD理事 竹田 保
能登半島地震による災害から1年が経過し、阪神淡路大震災から30年が経ったいま、避難所のバリアフリー化は、一定程度、進展してきたと思います。しかし、重度の障害を持つ私たちにとっては、依然として多くの課題が残されており、未だに災害のたびに避難生活を困難にしていると思います。
*
能登半島地域では、大地震や津波、洪水といった複数の災害に見舞われ、多くの方が断続的に被災しました。こうした厳しい状況下では、他者より多くのケアを必要とする重度障害者への理解と支援がこれまで以上に求められます。災害時の混乱の中でも、重度障害者は避難所での特別な配慮を必要とします。特に補助犬を伴う方の場合は、犬のケアも含めた支援が重要になります。
災害で避難した時に、重度障害者が直面する課題は多岐にわたります。適切な睡眠環境の確保、車いす対応のトイレ不足、体温調節の難しさなどが挙げられます。
東日本大震災では、震災による津波に飲み込まれただけでなく、低体温症により命を落とした人も多かったと聞いています。冬期の災害では、低体温症のリスクに対して、避難先での暖房対策を備えることも必要です。これに加え、補助犬の食事や健康管理も大きな負担となり得ます。必要な支援について平時からの準備と体制の構築が大事です。
避難所の環境改善や重度障害者への適切な支援のためには、平時からの啓発普及活動が不可欠です。地域社会への理解促進や専門知識の普及、広報活動を通じて、障害者と補助犬のニーズに対応する重要性を広めることが求められます。阪神淡路大震災などから学んだことを活かしながら、さらなる改善を図ることが大事だと思います。
*
日本筋ジストロフィー協会としては、障害者とその補助犬が安心して避難生活を送ることのできる環境について、重度障害者に適した避難設備の導入推進や、補助犬ケアに関する専門家との連携、地域住民・関係者向けの研修を進めて欲しいと思っています。災害時にも人間としての尊厳を保ち、安全で快適な生活ができる社会の実現を求めていきたいと考えています。
多くの災害が続く中、重度障害者と補助犬への理解と支援を広げ、阪神淡路大震災や東日本大震災からの教訓を礎に、誰もが安心して暮らせる社会を共に目指していきたいと思います。
■視点 「障害のある人の人権と社会保障裁判」の学びと確信
JD副代表 薗部 英夫
新春1月9日、オンラインで「読む会」があった。60人ほどが参加したこの会には「障害者問題研究」第52巻3号(全国障害者問題研究会発行):特集「障害のある人の人権と社会保障裁判」の「てい談」出席者が一堂につどった。JDでもお馴染みの藤原精吾弁護士(1941年生、堀木訴訟や優生保護法訴訟など担当)、井上英夫金沢大学名誉教授(1947年生、日本社会保障法学会代表理事など)、そして藤井克徳JD代表(1949年生、JDF副代表など)。まさに"レジェンド" たち3人だ。
戦後80年のなかで、朝日訴訟、堀木訴訟にはじまった社会保障裁判運動。1980年代の国際障害者年の衝撃。1990年代以降は永井訴訟(児童扶養手当の視覚障害者への公報義務)、学生無年金障害者訴訟などが続くが、社会福祉基礎構造改革という逆流のなかで「自助、共助、公助」論が根を下ろし、権利としての支援は「サービス」と置き換えられ、「応益負担」が強要された。そうした中での障害者自立支援法違憲訴訟と基本合意(2010年)。障害者権利条約を軸とした運動と政府とのせめぎ合い。浅田訴訟・天海訴訟(介護保険優先の65歳問題)、石田訴訟(24時間介護保障)などが続き、2024年7月3日最高裁大法廷の優生保護法訴訟全面勝訴判決だ。一つひとつの積み重ねがあり、今日の障害のある人の人権状況がかちとられてきたことが裁判と運動を支えてきた3人の言葉で語られ、深められている。このてい談はぜひ読んで欲しい。
*
「てい談」「読む会」の舞台裏をメモする。超忙しい3人の日程とつどう場の設定がわたしの最大のミッションだった。半年前から日程を調整し、収録したのは24年新春の京都(嵯峨野・学校共済の保養所)。ところが元日の能登地震で金沢の井上さんは移動できず、オンラインでつないだ。なんとか一堂に会したいと夏に能登で再度の合宿を設定するも台風が直撃。急遽オンラインの会合に。そして7月の優生裁判の「意義と課題」を追記し、推敲を重ねていただいた。
読む会では、「社会保障、人権保障の系譜、道のりを俯瞰することができた」「今後の展望に確信と希望が持てた」「裁判・人権運動は人を、組織を、記憶をつくってきた」「教育権の保障は、卒後や放課後、駅の改造・バリアフリーなど次のテーマを明らかにしてくれた」「裁判を闘う主体は当事者で、声を上げたことから、運動団体がその声を大きく広げ、ともに闘う中で弁護団も学んでいった」「判決はスタート。社会を変えていくことが大事」などの言葉には学びが凝縮されていた。
参加者からは、当時視覚障害のある学生で堀木訴訟を支援し「堀木さんの思いをみんなに知ってほしかった」「朝日さんは一人からの提訴だったけど今の生活保護(基準引下げ違憲)のいのちの砦裁判は5000人の原告ってすごい」「現場はいっぱいいっぱいだけどどんなことができるか考えたい」「勝つか負けるかだけでなくどう社会を変えるか」「積み上げてきた歴史に確信が持てた」「みんなで運動をつくっていくと、社会も自分も変わっていくことを実感する」など幅広い年齢層から発言が続いた。
*
わたしが全障研で働きはじめたのは1982年。7月7日が堀木訴訟大法廷の日。そこには「人権としての社会保障」の小川政亮先生が若き藤原弁護士とタッグを組み、院生だった井上さんが参加した。障害者自立支援法違憲訴訟と権利条約実現をめざすとりくみには藤井さんや藤岡毅弁護士らと運動を共にしている。運動が人をつなぎ、太らせ、広げて、道は拓かれてきた。一人ひとりの思いと歩みは、歴史をつくり、たしかに社会を変えている。
■JD2024年度特別セミナー 3月8日オンライン開催
なぜ、現行の年金・雇用制度では自立できないのか!
障害者の所得保障のあり方を問う
■2025年1月の活動記録
■ささえあい・つながり・わすれない
能登の障害のある人の現状とJDFの支援活動
塩田 千恵子(きょうされん常任理事)
■脱 優生思想
急がれる補償法の実現 -優生保護法裁判を終えて-
利光 恵子(優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)共同代表
/ 立命館大学生存学研究所客員研究員)
■国際支援 交流
カトマンズの病院で実現した難聴者支援 持続可能な意思疎通支援サービスの導入
宮本 忠司(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(全難聴)国際部)
■連載 出かけよう!おとなも読みたい えほん・児童文学の時空旅 第16回
北欧に恋して~せつ子さんのたくさんの本
品川 文雄(発達保障研究センター前理事長 / 元小学校障害児学級教諭)
■連載 障害者権利条約を補完する一般的意見をどう理解する? 第6回
一般的意見第5号(2017年)第19条 自立した生活及び地域社会への包容
―医療を、自立生活・インクルージョンを支えるものにする―
尾上 裕亮(障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)代表)
■連載 赤國青春記 第4回
~モスクワでただ一人、車いすの高校生~
古本 聡(翻訳業)
■連載エッセイ 障害・文化・よもやま話 第48回
映画「杳(はる)かなる」―ALSと共に生きる人の静かで饒舌なドキュメンタリー―
荒井 裕樹(二松学舎大学教授 / 障害者文化論研究者)
■トピックス・インフォメーション
■いんふぉめーしょん
賛助会員大募集中!
毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。
■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)
■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)
★1部300円(送料別)からお求めいただけます。
▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347
○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp
○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】
※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。
※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。
フッターメニュー