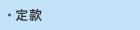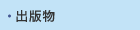25年5月26日更新
 2025年「すべての人の社会」5月号
2025年「すべての人の社会」5月号
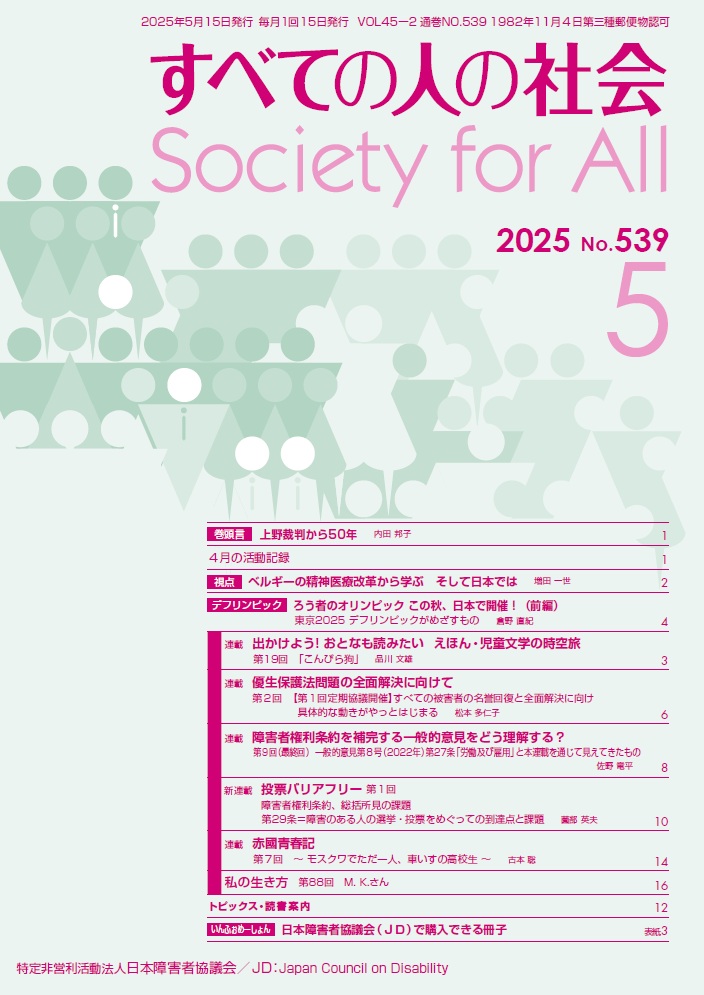
VOL.45-2 通巻NO.539
■巻頭言 上野裁判から50年
JD理事 内田 邦子
上野裁判をご存じでしょうか。
1973年2月1日、国鉄(当時)の高田馬場駅(東京都新宿区)で、鍼灸師の資格が取得できるヘレンケラー学院の学生だった全盲の上野孝司(たかし)さんがホームから転落し、入ってきた列車に巻き込まれて死亡し、ご家族が、国鉄が安全対策に対して不十分であったとして、損害賠償裁判を起こしたものです。
裁判が進む中で、偶々(たまたま)私の高校時代の担任教員と話した時、上野さんの事件を目撃したことを知りました。高田馬場駅で列車を待っていると、列車が何かを引きずっているようなバタバタする音が聞こえ、よく見るとそれはホームと列車の間に人が挟まれて腕が回転する音だったのです。「くれぐれもホームを歩くときは気をつけろよ」と話してくれたのを今でも忘れられず思い出されます。
裁判の傍聴や署名活動などの運動をしていく中で、国鉄に逆らったら逆効果、上野さんだって問題があったのでは…、など同じ視覚障害者のなかでも裁判に対して異議を唱える人たちもいましたが、視覚障害者はもちろん、国鉄の組合の人たちも一緒に運動に加わっての支援運動となっていきました。
ご両親が提訴したのは1975年2月19日でした。1979年3月27日に東京地裁で原告が勝訴し、国鉄が控訴、11年の歳月を経た1986年までに東京高等裁判所で和解が成立しました。判決では、視覚障害者の安全に努力することを国鉄に求めた勝利判決でした。その後の安全対策として、ホームドア整備の推進と、駅係員による転落防止・事故への対応に発展させることができました。
私も中途失明で、今はホームの縁(へり)にはあたりまえのように点字ブロックやホームドアが敷設されていますが、敷設されていなかった頃はホームの端に杖を当てながら移動していたものです。
50年以上前に起きた事故によって、ホームドア設置へと運動が広がってきましたが、人身事故は相変わらず後を絶たず、視覚障害者が駅ホームから落ちる事故は2010年から22年度の13年間に全国で883件(国土交通省の情報を集計)起きており、そのうち、落ちて車両と接触した事故が27件。そのほとんどが死亡事故です。
国土交通省は、2025年度までに全国3,000カ所、利用客1日10万人以上の駅で800カ所に増やす方針とされていますが、JRや私鉄での敷設率は56%となっており、まだまだ低い状態です。課題は山積しています。安全対策はもちろん、窓口の閉鎖などサービス面でも公共交通機関としての鉄道の役割を改めて求めるものです。
参考:全日本視覚障害者協議会発行「点字民報2025年2月号」
■視点 ベルギーの精神医療改革から学ぶ そして日本では
JD常務理事 増田 一世
◆ベルギーの精神医療改革から学ぶ
2018年2月、厳寒のベルギーを訪問した。EU諸国の中でも精神医療改革が遅れていたベルギーが改革に向け動き出し、入院中心の精神医療から地域へという動きが本格化していた。しかも日本と同様に民間精神病院中心だという。ぜひ、現地視察をということで有志による視察団を組織し、1年ほどかけて現地のことを学び、出向いた。
それから、7年の歳月が経った。視察後「共同創造の精神保健福祉をすすめる会」を組織し、当事者、家族、医療・福祉関係者が集まり、継続的にベルギーの精神医療改革から何を学び、日本でどう生かすのかを考えてきた。ベルギー保健省で精神医療改革を中心的に担ってきたBernard Jacobさんを2回(2019、2025)お招きし、新型コロナウイルス感染拡大期にはオンラインで精神障害のある人と家族との交流学習会を開催してきた。
◆共通理念 リカバリーとコ・プロダクション(共同創造)
ベルギーの精神医療改革の中心にリカバリーがある。病気の症状や障害に着目するのではなく、その人がどのような暮らしや人生を望んでいるのか、本人のニーズを中心にした支援への転換だ。私は長年精神障害を経験してきた人たちとかかわりながら、病気や障害は環境によって軽くも重くもなること、地域でさまざまな人と出会い、生き方を回復していくことを実感してきた。まさに障害者権利条約が求める医学モデルから社会モデル/人権モデルへの転換が求められている。
そして、もう1つの共通理念がコ・プロダクションだ。自分自身の治療や回復過程において、主人公は自分自身であり、さまざまな人の意見を聞きながらも自身の考えが尊重される。それは治療関係にとどまらず、福祉的な事業所の運営や地域や国の制度や施策を検討する際にも重要な考え方となっている。ベルギーではピアスタッフや家族の経験を生かした活動も活発であり、影響力がある。
この2つの理念を共通のものとしながら、ベルギーの精神医療改革は進められてきた。病床を減らして、地域のモバイルチームに転換するということもこの2つの理念に沿ったことである。現地視察の際に何人もの人から、病院のベッドの上で治療を受けるのと住み慣れた地域で、家で安心できる環境で治療や支援を受けるのと、どちらが患者にとって有効と思うかと投げかけられた。精神障害があったとしても生活するのは地域であり、生活を継続しながら治療や支援を受けるという当たり前を実現しているのがベルギーなのだ。
◆日本の精神医療・保健福祉を当たり前のものにしていく
この当たり前を日本でどう実現するのかが問われている。この2月に開催したBernard Jacobさんを招いての学習会には対面とオンライン合わせて400人ほどの人が参加した。参加者は多様だった。日本でも精神医療改革が必要だと考えている人の広がりとも考えられよう。
Bernard Jacobさんは2度の来日の際に「コミュニケーション、コミュニケーション、コミュニケーション」と強調した。複数の言語圏、地域政府があるベルギーでの意思決定の困難さを経験したからのことであろう。日本でも「本人中心」に精神医療・保健福祉を見直してみることが必要ではないか。精神障害のある人や家族の体験には価値があることを共通認識とし、彼らの体験の中での気づきや意見に耳を傾け、学ぶ必要がある。まずはそこから始めたい。
■2025年4月の活動記録
■デフリンピック ろう者のオリンピック この秋、日本で開催!(前編)
東京2025 デフリンピックがめざすもの
倉野 直紀(全日本ろうあ連盟 / デフリンピック運営委員会 事務局長)
■連載 出かけよう!おとなも読みたい えほん・児童文学の時空旅 第19回
「こんぴら狗(いぬ)」
品川 文雄(発達保障研究センター前理事長 / 元小学校障害児学級教諭)
■連載 優生保護法問題の全面解決に向けて 第2回
【第1回定期協議開催】すべての被害者の名誉回復と全面解決に向け具体的な動きがやっとはじまる
松本 多仁子(優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会事務局長)
■連載 障害者権利条約を補完する一般的意見をどう理解する? 第9回 (最終回)
一般的意見第8号(2022年)第27条「労働及び雇用」と本連載を通じて見えてきたもの
佐野 竜平(日本障害者協議会理事 / 法政大学現代福祉学部教授)
■新連載 投票バリアフリー 第1回
障害者権利条約、総括所見の課題
第29条=障害のある人の選挙・投票をめぐっての到達点と課題
薗部 英夫(日本障害者協議会(JD)副代表)
■連載 赤國青春記 第7回
~モスクワでただ一人、車いすの高校生~
古本 聡(翻訳業)
■私の生き方 第88回
M.K.さん(立教大学2年)
■トピックス・読書案内
■いんふぉめーしょん
賛助会員大募集中!
毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。
■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)
■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)
★1部300円(送料別)からお求めいただけます。
▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347
○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp
○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】
※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。
※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。
フッターメニュー