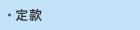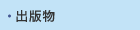25年5月16日更新
 神田裕子著『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』に関する見解
神田裕子著『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』に関する見解
○三笠書房より4月22日に出版された書籍について、JDの見解を出版社に送付しました
2025年5月15日
(株)三笠書房 御中
神田裕子著『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』に関する見解
NPO法人日本障害者協議会(JD)代表 藤井 克徳
本協議会(略称:JD)は、1980年4月、国連・国際障害者年(1981年)を成功させようと、障害のある本人、家族、施設、専門職、研究者等が大同団結して発足しました。障害関連の調査研究や情報提供、政策提言、啓発活動などを行ない、日本も批准した障害者権利条約を国内で実質化するための取り組みを進めています。現在、58団体から成り、日本自閉症協会や日本発達障害連盟なども加盟しています。
貴社が本年4月22日に刊行した標記書籍については、発刊前から多くの批判があり、それらに対する4月18日付けの貴社及び著者の見解も確認いたしました。刊行された書籍を拝読し、「記載内容に納得できる点」と、障害者権利条約の視点からも人権侵害となるので「改訂を求めたい問題点」とに整理し、本協議会としての見解をお伝えします。現行のまま増刷・販売等が行なわれることは、多くの生きづらさや困難を抱えている方々への人権侵害になると言わざるをえません。早急に検討を重ね、差別や偏見を生むことのない書籍に改訂していただくことを強く求めます。
なお,当方の見解はHPに掲載することをお断りしておきます。そして、本文書が指摘する諸点について、貴社のお考え及び今後の取組について、ご返信をお願いいたします。
1.記載内容に納得できる点
本書のすべてを否定するものではなく、第1章では、職場で誤解を生みやすい「ASD」「ADHD」「愛着障害」「トラウマ障害」「世代ギャップ」「疾患」という6タイプの特性、それぞれの痛みにいかに寄り添うかが詳述されている。また、「カウンセリングマインド」として、共感的理解、受容、アサーションスキル、Iメッセージなどを整理していることなど、著者のカウンセラー歴40年の蓄積が反映され、参考となる点もある。終章の「自分軸」の発想や、「異なる価値の人と折り合いをつける」なども大切な観点である。
2.改訂を求めたい問題点
ただし、看過できない記述も多いと言わざるをえず、以下に改訂を求めたい主要な問題点を指摘する。
① まず、「困ったさん」という言葉を文中で躊躇なく用いている姿勢には、貴社のコンプライアンス、著者の倫理観などに疑問を抱かざるをえない。「困ったさん」には明らかに「迷惑な人」という差別的・排除的な意味合いが込められ、そのように呼ばれた人々が痛みを感じざるをえないことへの配慮がない。施設職員などがこの言葉を用いたら、障害者虐待防止法により「虐待」と認定されかねない。すなわち、職場で起こる問題を個人の責任に帰す医学モデル偏重であり、差別意識を助長するなど社会全体に与える影響が大きい。
② 人間を動物に例え、イラスト化したことも尊厳を損なう手法であり、出版予告の文章も差別感が露骨で、目次の記述も煽情的な表現が並んでいる。誰もが働きやすい職場をめざしての刊行であるはずだが、「売らんかな!」という商業主義一辺倒と感じざるをえない。このような編集方針を改めていただくことを強く要望する。
③ 第3章の「『困ったさん』をうまく動かす」というタイトルや「攻略」などの言葉は、上から目線の「おごり」や差別意識そのものである。5つのタイプについて職場での「困った」シーン、具体的な対策を紹介している。しかし、タイプごとの「決めつけ」といった印象を拭えず、文中に「尊重」といった言葉も登場するが、一人ひとりの「尊厳」が損なわれていると考えざるをえない。この章では著者のカウンセラーとしての資質に疑問を感ずる記述も多く、抜本的な修正をお願いしたい。
④ 本書全体を通して差別的・排除的な思考や記述を削除し、障害者権利条約の社会モデル・人権モデルの視点を踏まえた、真に共生社会の実現に資する書籍とすべく確実な検討を重ねていただきたい。そのためには、職場だけでなく地域や行政へのアプローチも視野に入れ、社会全体の改革に寄与する書籍として改訂されることを願ってやまない。
フッターメニュー