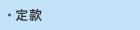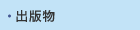25年2月13日更新
 緊急声明 高額療養費制度における負担上限額の引き上げについて
緊急声明 高額療養費制度における負担上限額の引き上げについて
○高額療養費の負担上限額の引き上げについて、JDから緊急声明を発表しました
2025年2月12日
緊急声明
高額療養費制度における負担上限額の引き上げについて
NPO法人日本障害者協議会(JD)
代表 藤井 克徳
政府は2025年8月と2026年8月の二段階に分けて、高額療養費制度の負担上限額を引き上げるとしています。高額療養費制度の引き上げは公的な医療費助成制度のない長期慢性疾患や難病のある人たちなど、中長期にわたり高額な治療の継続が必要な患者や家族に多大な影響を及ぼします。また、この問題は所得水準の乏しい障害者全体にも甚大な影響をもたらします。負担増によって受診を抑制し、治療選択を狭め、その結果、重症化の危険、治療継続の断念につながり、生活の崩壊や命の危機にも直結しかねません。
障害者権利条約では、政策決定過程で障害のある人たちの声を聴き、決定に参画させることを国や自治体に求めています。本人不在の決定は障害者権利条約に反しています。また、2022年9月に出された国連・障害者権利委員会からの勧告では、費用負担能力に基づいた医療費補助金の制度が不十分であると指摘されています。さらに「費用負担能力に基づいた医療費補助金の仕組みを設置し、これらの補助金を、より集中的な支援を必要とする者を含めた全ての障害者に拡大すること」を求めています。この勧告に逆行する動きであり、容認できません。
石破総理大臣の施政方針演説には、冒頭で「国民1人1人の幸福実現」を掲げつつ、後段では「高額療養費制度の見直しなどにより保険料負担の抑制につなげる」とあります。高額療養費制度を利用している人たちへの影響や実態をどれほど理解しての発言なのでしょうか。
がんをはじめとする命にかかわる疾患、難病や長期的に治療が必要な人たちから、負担上限額引き上げが、いかに大きな影響を及ぼすのか、危機的な状況を訴える声が数多く上がっています。政府は、負担上限額引き上げの決定の際にどれだけ患者やその家族の声を聴いたでしょうか。中長期にわたって高額な治療が必要な人たちの生活実態や影響を把握したうえでの決定だったのでしょうか。多数回該当の人には限度額の見直しを検討されているようですが、それで今般の負担上限額引き上げの影響がなくなるわけではありません。
中長期の治療の必要な人たちの生活実態や障害者の所得状況を無視し、何より当事者の声を軽視した今般の引き上げ案については、ただちにこれを撤回すべきです。
参考 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
(平成22年1月7日)一部抜粋
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を,立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心からの反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施にあたる。
フッターメニュー