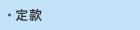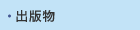25年11月4日更新
 2025年「すべての人の社会」10月号
2025年「すべての人の社会」10月号
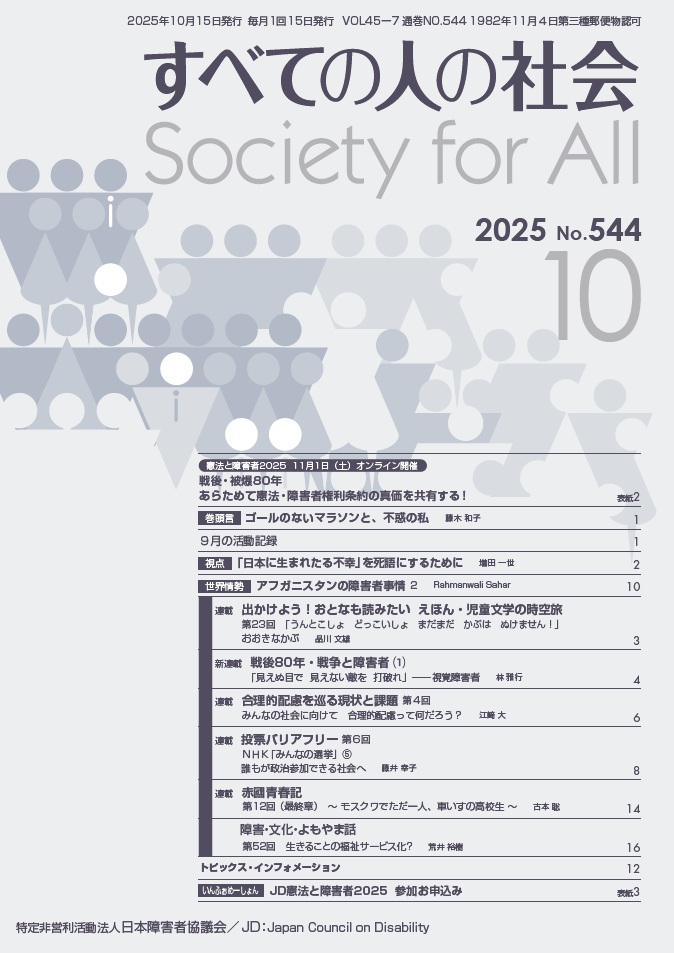
VOL.45-7 通巻NO.544
■巻頭言 ゴールのないマラソンと、不惑の私
JD理事 藤木 和子
今度の11月には東京で「デフリンピック」が開かれ、世界中から聴覚障害のあるスポーツ選手たちが日本に集まります。そして12月には、日本弁護士連合会の人権大会が長崎で行われます。テーマは「インクルーシブ教育」です。
私は耳が聞こえない弟と育った「きょうだい」であり、弁護士・手話通訳士でもあります。デフリンピックは友人の応援に行く予定です。また、この機に「聞こえないきょうだいのいる私たち」というテーマで新聞にも取り上げていただきました(読売新聞オンライン、2025年6月22日)。日弁連の人権大会では、私は名ばかりの実行委員ですが、まずは委員会そのものがインクルーシブになるよう、手話・字幕を含めたコミュニケーションや情報保障を担当し、きょうだい児への配慮も呼びかけています。もっとも今は、親の病気をきっかけに「親亡きあと」に向き合い、自分自身も一度立ち止まりたいと考えて、仕事や活動を少しセーブしています。JD理事会もお休みが多くなっており、ご心配をおかけしていますが、私自身は元気に過ごしています。
障害児者のきょうだいの三大悩みは、拙書のタイトルにもした『進路・結婚・親亡きあと』(中央法規出版)です。私自身、「進路・結婚」については情報も相談相手もなく、もがきながらの手探りでした。しかし「親亡きあと」に向けては、多くの経験者の話を聞き、相談できるつながりもあるので、不思議な安心と穏やかさを感じています。母は弟を育てることに全力を注ぎ、父は仕事と付き合いで忙しい、そんな家族でしたが、近年は、私のきょうだいの活動を応援してくれるようになり、食事や旅行も共に楽しめるようになりました。長い時間を経てようやく家族が一つになれたような気がします。
振り返れば、弁護士になった頃に「きょうだいのことを知ってほしい!」と旗を掲げ、あっという間に15年近く走り続けてきましたが、最近ようやく「これはゴールのないマラソンだ」と気付きました。40代になった今、これからの20年、40年、あるいは60年を思うと、正直途方に暮れる気持ちもありますが、JDの先輩方の背中を見ていると心強いです。良い意味で、悩む気力や体力もほどよく抜けてきたところで、これからは遠慮せずに不惑でいきたいです。
デフリンピックも、日弁連の人権大会「インクルーシブ教育」も、そして皆様の日々の生活や活動も、それぞれの人がそれぞれの場で生きる姿が社会を変えていく力を信じています。私も、自分の歩幅とペースで一歩ずつ、確かに進み続けたいと思います。
■視点 「日本に生まれたる不幸」を死語にするために
JD常務理事 増田 一世
◆精神病床数5.2万床過剰と財務省の指摘
2025年6月13日、次年度の予算方針を示す「経済財政運営と改革の基本方針2025」、いわゆる骨太方針が示された。骨太方針に先立って5月27日、財政制度等審議会財政制度分科会(十倉雅和会長)が、「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」という文書を財務大臣に提出。
注目したいのは、この文書の中で「医療」に言及する部分である。地域医療構想が1つのキーワードであり、その中で「精神病床」という見出しで「精神病床数については、諸外国比でも、基準病床数比でも、今なお過剰。新たな地域医療構想には精神病床も対象予定。近年の介護・障害福祉サービスの充実や診療所・在宅医療との連携とあわせて、精神病床の適正化が一層求められるが、現状でも、長期入院患者の地域移行が十分に進んでいるとは言えない」とある。そして、添付の資料には精神病床数の国際比較があり、いかに日本が突出して精神病床(32.2万床)が多いか、一方精神病床の利用率が低下(81.6%)していることを示している。そして1年以上入院している患者は約15.2万人(入院患者の約60%)であり、第はちじ医療計画(2024~2029)では各都道府県が定める基準病床数は26.6万床であり、5.2万床過剰であるとデータで示している。国も作り過ぎた精神病床の対策に重い腰を上げたということなのか。あるいは医療費削減の視点からの病床削減なのか。
日本精神科病院協会(日精協:民間精神科病院の全国組織)の会長も「少子高齢化による疾病構造の大きな変化、従業員確保のリスク、統合失調症モデルで2040年問題を乗り越えられるのかと考えた時に、地域医療構想に参画して2040年以降の精神科地域医療モデルを日精協主導で真剣に考える時期に来ている」(日精協雑誌43巻10号,2024)と述べている。精神病床削減の方向性を、国も日精協も合意したようにみえる。では、病床を減らして精神科病院はどのような役割を果たしていくのか。あるいは1年以上入院している患者たちを地域でどう受け止めるのか。10年ほど前、増え過ぎた精神病床を転換して居住系施設にしようという政策が提案されたが、全国的な反対運動が起こり、実現しなかった。またぞろこんな安直な構想が出されてくるのではないかという危惧もある。
◆「日本に生まれたる不幸」を死語にするチャンス
もう1つの危惧は、障害者総合支援法によって規制緩和が進み、グループホームなど量的な拡大は進んだが、障害者福祉の専門性が低下していることだ。ある営利法人は「素人でもできる仕事」と求人広告にうたう。こうした状況を踏まえつつも「日本に生まれたる不幸」を死語にしていくために市民社会が考え、提案し、実現に向けて行動することが今こそ重要なのではないか。
そして、病床削減を目的化することは危険だ。病床削減後の日本の精神科医療の姿を描かなくてはならない。発症前の不安定な時期に適切な支援につながることができるのか、発症時にどれだけ適切な支援につながれるのか、正しい情報や療養について生きた情報を得られるのか。家族ではなく、社会全体で支える仕組みはどうするのか。病状が不安定になった時に地域で治療を受けられる仕組みをどう用意するのか……今こそ当事者や家族との対話が重要だ。ボトルネックはどこにあるのか、何が必要なのか、幅広く声を聴き、構想を練るべきだ。行政に都合のよい委員だけを集めるのはやめにして、多様な意見を持つ人たちが対等に議論し、改革の方向性を描き出すことが求められている。市民社会の本領発揮の時としたい。
■2025年9月の活動記録
■憲法と障害者2025 11月1日(土)オンライン開催 戦後・被爆80年 あらためて憲法・障害者権利条約の真価を共有する!
■世界情勢 アフガニスタンの障害者事情 2
Rahmanwali Sahar(ミルワイス・カーン・ニカ・ザブル高等教育機関経営学部講師)
■連載 出かけよう!おとなも読みたい えほん・児童文学の時空旅
第23回 「うんとこしょ どっこいしょ まだまだ かぶは ぬけません!」 おおきなかぶ
品川 文雄(発達保障研究センター前理事長 / 元小学校障害児学級教諭)
■新連載 戦後80年・戦争と障害者 (1)
「見えぬ目で 見えない敵を 打破れ」―視覚障害者
林 雅行(ドキュメンタリー映画監督・作家)
■連載 合理的配慮を巡る現状と課題 第4回
みんなの社会に向けて 合理的配慮って何だろう?
江﨑 大(杉並区保健福祉部障害者施策課事業推進係長)
■連載 投票バリアフリー 第6回
NHK「みんなの選挙」5
誰もが政治参加できる社会へ
藤井 幸子(NHKコンテンツ制作局 第1制作センター・福祉班 ディレクター)
■連載 赤國青春記
第12回(最終章) ~モスクワでただ一人、車いすの高校生~
古本 聡(翻訳業)
■障害・文化・よもやま話
第52回 生きることの福祉サービス化?
荒井 裕樹(二松学舎大学教授/障害者文化論研究者)
■トピックス・インフォメーション
■いんふぉめーしょん
賛助会員大募集中!
毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。
■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)
■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)
★1部300円(送料別)からお求めいただけます。
▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347
○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp
○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】
※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。
※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。
フッターメニュー