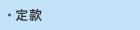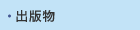25年3月24日更新
 2025年「すべての人の社会」3月号
2025年「すべての人の社会」3月号
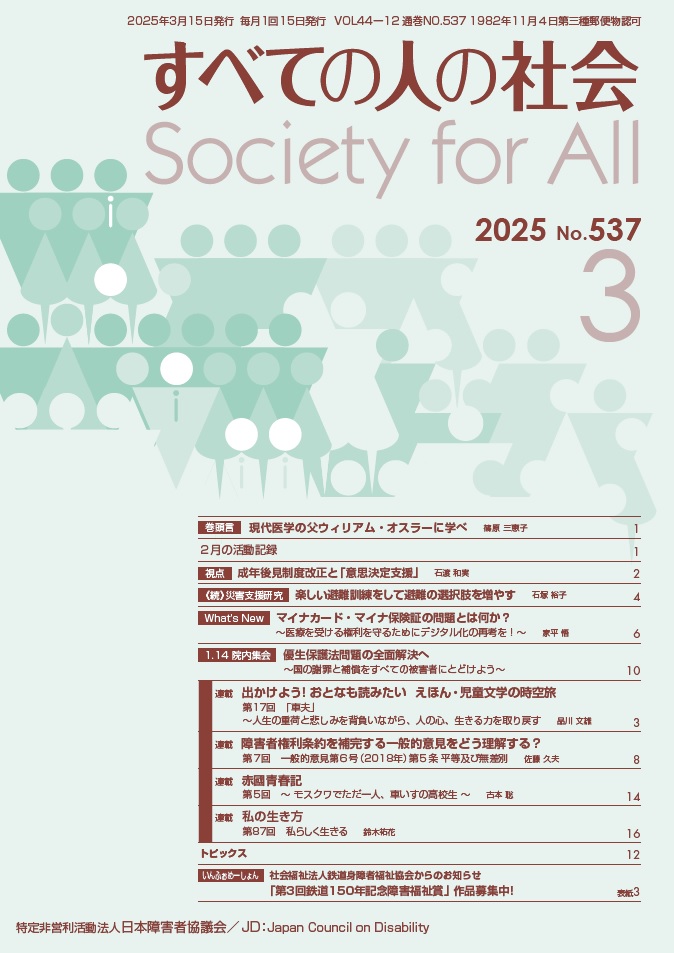
VOL.44-12 通巻NO.537
■巻頭言 現代医学の父ウィリアム・オスラーに学べ
JD理事 篠原 三恵子
故日野原重明医師が敬愛したウィリアム・オスラーは、「現代医学の父」と呼ばれ、病気の重要な特徴を識別するために、患者の声に耳を傾けることの重要性を強調していました。しかし、現代医学は診断のための検査に、あまりにも依存し過ぎているのではないでしょうか。
2024年6月に米国屈指の医学諮問機関である全米科学・工学・医学アカデミーズが出版した「Long COVID(コロナ後遺症)の定義」では、Long COVIDを新型コロナウイルス感染後に発症する感染症関連の慢性疾患(IACCs)と定義し、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)、体位性頻脈症候群などの既知のIACCsを発症する可能性をあげています。
ME/CFSは以前から、ほとんどの患者がウイルス感染後に発症することが知られていましたし、感染症を誘因として発症する様々な慢性疾患があることは何十年も前から認識されていました。しかし、軽度のウイルス性疾患と思われる場合、病原体を特定する検査が行われることは稀で、IACCsを発症したと認識される頃には、一般的検査で病原体を特定できる時期は過ぎており、発症原因は特定されないまま終わってきました。
対照的に、今回はパンデミックであったために、Long COVIDの誘因となったウイルス感染は明確に記録され、この問題に注目が集まりました。まさにこのパンデミックは、IACCsの病態や発症メカニズム、症状の管理等を解明する絶好の機会なのです。その際には、IACCsの一つであるME/CFSの何十年にも及ぶ研究が役に立つはずです。
米国国立衛生研究所は2016年に、「疾病のリスクと治療標的を特定するために、革新的な生物医学的研究が早急に必要である」との結論を下しました。一方、厚労省は未だに国会議員へのレクチャー資料で、「ME/CFSは身体診察や臨床検査で客観的な異常が認められない状況で、日常生活を送れないほど重度の疲労感が長期間続く状態をいい、その原因は身体的なもの、精神的なものを含めわかっていない」と説明しています。
ME/CFSはWHOで神経系疾患と分類され、国際的に認められた診断基準が存在し、国立精神・神経医療研究センターで治療薬の治験が開始されています。バイオマーカーはまだ見つかっていませんが、多くの検査で異常が認められ、臨床的診断基準による診断・治療・研究が世界中で行われています。
2014年の厚労省の実態調査で3割の患者が寝たきりに近いという深刻な実態が明らかになっており、患者の救済は急務です。ウィリアム・オスラーに学べ!
■視点 成年後見制度改正と「意思決定支援」
JD副代表 石渡 和実
成年後見制度改正の動向については、本誌(2023年10月号)でも紹介させていただいた。2024年4月9日より、法務省法制審議会民法(成年後見等関係)部会で本格的な議論が開始され、2027年に改正法施行の見込みである。
2000年4月、介護保険制度の開始とともにスタートした成年後見制度は、「最善の利益」のために取消権を行使できるなど、本人の意思を否定するむしろ人権侵害の法律、との批判は障害分野では顕著であった。海外も同様で、障害者権利条約12条「法律の前にひとしく認められる権利」の成立に至り、「一般的意見1号」が出され、「意思決定支援」の実践がさまざまな分野に広がっていく。
後見・保佐・補助の3類型が一元化され、遺産相続など後見制度は必要な時だけ利用し、終了できるということが一番の注目点である。「スポット後見」などとも言われ、後見報酬を払うのも利用中だけとなり、障害関係者には歓迎できる方向性と言えよう。一方で、「親亡き後」を後見人に委ねるといった風潮もある中で、障害がある人の長い人生を地域でいかに支えるかは改めて課題となっている。
改正論議でも成年後見制度で暮らし全体をカバーするのではなく、医療や福祉サービスとの連携、地域の支え合いなど、地域の支援ネットワーク、「権利擁護支援」のあり方が注目されている。そして、この地域生活支援は本人が望む暮らし、意思を尊重した支援であることは言うまでもない。意思をどのようにして育み(意思形成)、それを支援者や周囲に伝え(意思表明)、想いを現実のものにできるか(意思実現)、という意思決定支援のプロセスを丁寧に進めていくことが求められている。
障害者の意思決定支援ガイドライン(2017年)では、意思決定支援を「本人の意思の確認や意思(will)及び選好(preference)を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討する」と定義している。日本が権利条約を批准した2014年1月頃は、「最善の利益」のために後見人等が代わって判断するという「代理決定容認説」が国際的にも一般的であった。しかし、2014年4月に採択された一般的意見1号では、「『最善の利益』の原則は、成人に関しては12条を遵守する安全装置にはならない」と「最善の利益」を否定する。また、「法的能力とは、障害のある人を含むすべての人が、単に人間であるという理由に基づき(simply by virtue of being human)法的地位と法的主体性を有する」との人間観に立つ。制度改正の議論でも、「遷延性意識障害の人であっても、快・不快の感情はあり、意思もある」といった意見が注目されている。
筆者は今年1月、30年来関わっている法人の「実践発表会」に参加した。ここでは保育園と児童発達支援センターとが同じ空間にあり、さまざまな子ども達が交流を深めている。5年間利用している医療的ケア児の支援について、動画で報告が行われた。チューブ栄養で言葉を発することができないA君の意思を汲み取り、その想いを実現するための試行錯誤を続けてきたのだという。「これでいい?」と問い続けた5年間だったという。しかし、保育士や看護師との間に信頼関係が築かれ、動作や表情などでA君との意思疎通が進み、A君もお友達も、何より支援者が大きく成長したと実感させられた。卒園旅行で初めて電車に乗ったA君が感激の涙を流し、動画を見ていた参加者も涙し、人間の持つ力を再認識させられた場であった。誰もが意思を持ち、自分らしく生きることで周囲や地域を変えていく。まさに、意思決定支援の積み重ねは地域共生社会を実現するためのプロセスである。
参考:
「特集 成年後見制度改革」『ジュリスト』 No.1596,2024年5月
■2025年2月の活動記録
■《続》災害支援研究
楽しい避難訓練をして避難の選択肢を増やす
石塚 裕子(東北福祉大学 教授 / 一般社団法人日本福祉のまちづくり学会 副会長)
■What's New
マイナカード・マイナ保険証の問題とは何か? ~医療を受ける権利を守るためにデジタル化の再考を!~
家平 悟(障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協)事務局長)
■1.14 院内集会
優生保護法問題の全面解決へ~国の謝罪と補償をすべての被害者にとどけよう~
■連載 出かけよう!おとなも読みたい えほん・児童文学の時空旅 第17回
「車夫」~人生の重荷と悲しみを背負いながら、人の心、生きる力を取り戻す
品川 文雄(発達保障研究センター前理事長 / 元小学校障害児学級教諭)
■連載 障害者権利条約を補完する一般的意見をどう理解する? 第7回
一般的意見第6号(2018年)第5条 平等及び無差別
佐藤 久夫(NPO法人日本障害者協議会理事)
■連載 赤國青春記 第5回
~モスクワでただ一人、車いすの高校生~
古本 聡(翻訳業)
■連載 私の生き方 第87回
私らしく生きる
鈴木 祐花(福島県在住)
■トピックス・インフォメーション
■いんふぉめーしょん
社会福祉法人鉄道身障者福祉協会からのお知らせ 「第3回鉄道150年記念障害福祉賞」 作品募集中!
賛助会員大募集中!
毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。
■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)
■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)
★1部300円(送料別)からお求めいただけます。
▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347
○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp
○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】
※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。
※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。
フッターメニュー